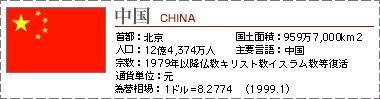 |
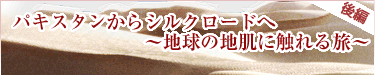 |
 ようやくクンジュラーブ峠を越え、ススト(ソスト)で出国手続きを済ませたあと、中国側の国境の街タシクルガンに入った。
ようやくクンジュラーブ峠を越え、ススト(ソスト)で出国手続きを済ませたあと、中国側の国境の街タシクルガンに入った。「タシクルガン」は、タジク語で「石の城」を意味するという。その名の由来となった石頭城を見学した。小高い丘の上に立つこの城からは、周囲の景観が一望できる。視界をさえぎる高い建物がほかにないため、はるか彼方まで見渡せるのだ。 青というより紺碧に近い空が広がり、美しい稜線を見せる山々に囲まれた、静かな街。その街を囲むのは、カラコルム山脈、ヒンズークシ山脈、それにパミール山脈の山々だ。季節は真夏であったが、高原の風は乾いてさわやかだった。その風にあたりながら、しばしの間、雄大な景観に見とれていた。 「幻の湖」と呼ばれるカラクリ湖もまた忘れ難い。7000メートル級の高山――日本の最高峰・富士は3776メートルだから、この地の山々のスケールはケタちがいだ――に囲まれた、深く大きな湖である。面積は364平方キロ。 カラクリ湖のほとりにある宿泊所に泊まり、翌朝はバスでカシュガルに向かった。中国西端のオアシス都市であり、ウイグル族の町だ。バザールなどを見て回ると、「ほんとうにここは中国なのだろうか?」と不思議になるほどイスラム文化の影響が濃い。羊の肉が焼ける匂い、コーランを唱える声、人々の顔立ちや衣裳、町の中心にあるエイティガール寺院(モスク)……どれをとってもイスラム都市そのものなのだ。 しかし、この不思議な“異文化の混在”こそ、この街がシルクロードの要衝であった証といえる。カシュガルは、古来より東西を行きかう人々の休息地として栄え、かの玄奘やマルコ・ポーロも立ち寄ったという。 いにしえの隊商の道程をたどるかのような、シルクロードの旅はつづく――。 カシュガルを離れた私は、古来より「絹都」と呼ばれたというホータンへ向かった。絹製品の名産地であったことから「絹都」の名があるというこの街のバザールでは、いまでも民族衣装に使われる矢絣の布がたくさん売られていた。 ホータンから、タクラマカン砂漠の天山南路を通り、アクス経由でクチャ(庫車)へ向かった。 このクチャこそ、シルクロードの中心地ともいうべき都市である。漢代の歴史書『前漢書』の「西域伝」にも登場するほど古い都市であり、玄奘三蔵も2ヶ月にわたって滞在したという。また、多くの仏典を漢語に訳した名僧・鳩摩羅汁(344〜413)を生んだ都でもある。古代から栄えていたというのみならず、そうした歴史的経緯からいっても、クチャを見ずしてシルクロードは語れない。 歴史のある街だから、クチャにはあちこちに貴重な遺跡がある。私たちも、スバシ古城やキジル千仏洞などに立ち寄った。 キジル千仏洞は、岩山に彫られた石窟で、その規模は敦煌の莫高窟にも匹敵するといわれる。ただし、敦煌に比べると保存状態が悪く、あまり壁画などが残っていない。が、それでも往時の繁栄ぶりが偲ばれて興趣尽きない。 クチャからコルラを経由し、トルファンへ――。 トルファンは、30分もあれば市街地を歩き通せるくらいの小さな町である。町の交通機関として馬車ならぬ「ロバ車」が走っているが、なるほど、この狭さならロバにゆっくり引かれていったほうがよいだろう。  「オアシスの町」の別名があるとおり、トルファンは、シルクロードのほかの都市に比べて突出して緑が多い。天山山脈の麓にあり、その雪解け水が町中を潤しているためだ。町に住む人たちも素朴で人懐っこく、邪気のない笑顔を向けてくる。
「オアシスの町」の別名があるとおり、トルファンは、シルクロードのほかの都市に比べて突出して緑が多い。天山山脈の麓にあり、その雪解け水が町中を潤しているためだ。町に住む人たちも素朴で人懐っこく、邪気のない笑顔を向けてくる。荒涼たる砂丘や急峻な山道など、大自然の厳しさをさんざん味わった末にトルファンを訪れたため、心の底から癒されるようだった。 パキスタンからシルクロードへと、地球の地肌に触れるような20日間の長い旅は、こうして終わった――。 (1999年8月) |